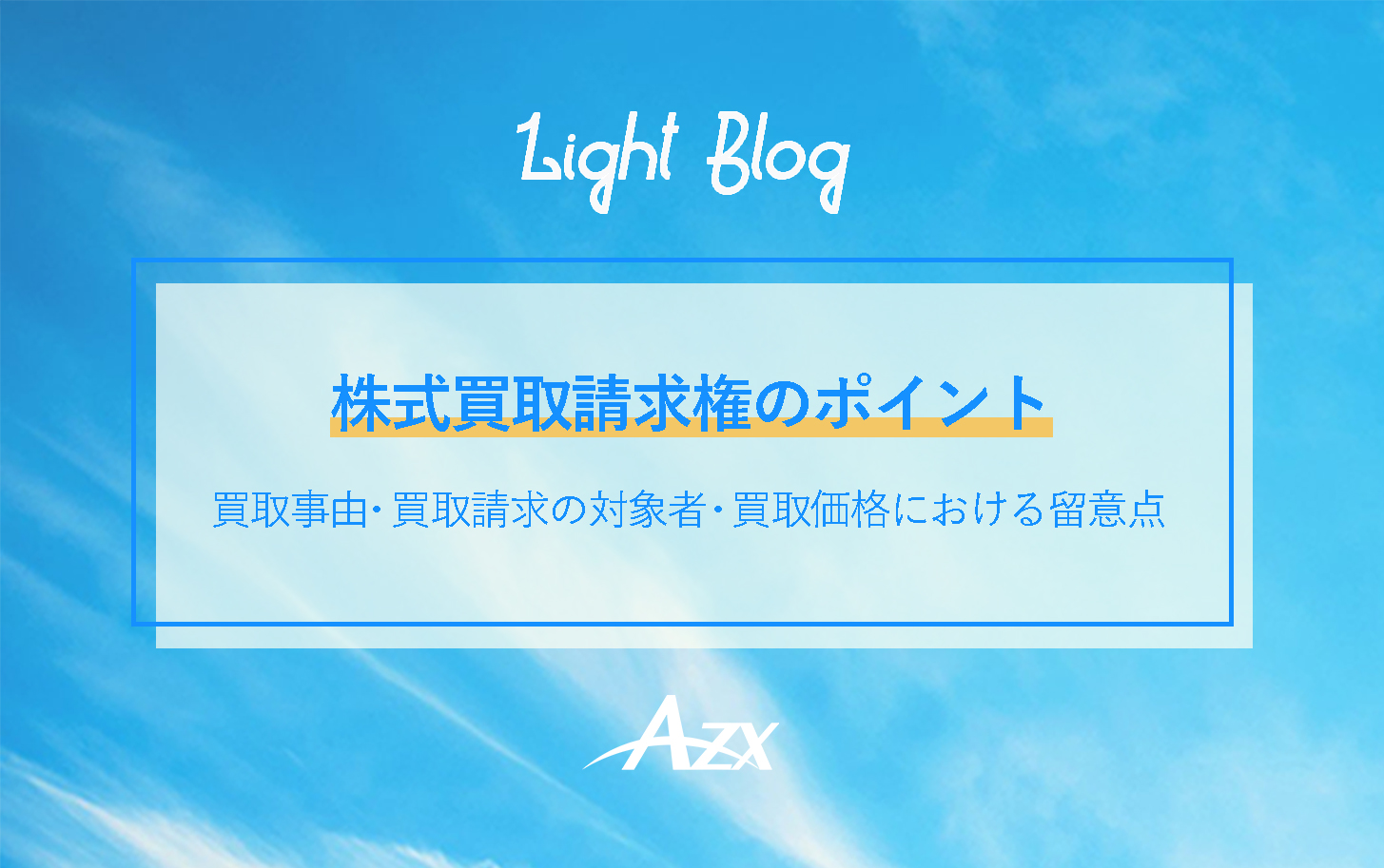
AZX弁護士の平井です。
今回は投資契約書のうち、株式買取請求権について解説したいと思います。
目次
1. 株式買取請求権が定められている理由
株式買取請求権は、投資契約の規定に違反した場合や表明保証の内容が真実と反することが発覚した場合などに、投資家が有しているスタートアップの株式を買い取るように請求することができる権利になります。
発行会社又は経営株主が、投資契約の規定に違反した場合、契約違反である以上、民法に基づく債務不履行としての損害賠償請求が理論上は可能です。この場合、損害賠償を請求する側は、損害額を主張立証する必要があります。
しかし、投資契約では、この損害額の主張立証が極めて困難なケースがあります。例えば、新株発行には投資家の事前承諾が必要であるという規定に違反して会社が新株発行をした場合や、投資家の取締役指名権を無視されて取締役の派遣を拒絶された場合に、投資家に生じた損害額を主張立証することは困難です。投資契約の多くの規定については、違反された場合に損害額の主張立証することは困難なケースが多く、投資契約違反に対するサンクションとして株式の買取りを定める必要が、投資家としては生じます。
また、投資家にとって、投資契約に違反するような企業に対する投資を継続することは難しく、株式を売却する必要が生じ、この面からも株式の買取を請求する必要が生じます。
このような理由から、日本の投資契約では、株式買取請求権が定められているケースが多いです。
2. 買取事由
株式買取請求権における買取事由として定められる典型的なものは以下の3つです。
株式買取請求権が行使されたときのインパクトはかなり大きいため、スタートアップ側としては、できるだけリスクを低減する観点から、買取事由を自らがコントロール可能な範囲に限定するように交渉することが考えられます。
(1) 投資契約違反
(2) 表明保証違反
(3) 株式上場の要件を満たしているのに上場しない場合
(1) 投資契約違反
スタートアップとしては、投資契約違反については、意図しない軽微な違反で株式買取事由に該当することを避けるため、違反について是正要求があっても一定期間内に是正しない場合などに限定することが考えられます。また、対象を重要な規定に限定することも考えられます。
この点については、2022年3月31日に公正取引委員会及び経済産業省が策定した「スタートアップとの事業提携及びスタートアップへの出資に関する指針」において、買取請求権の行使条件については「買取請求権の行使が正当と認められる重大な表明保証違反、重大な契約違反」に限定すべきと指摘されていることから(同指針45頁)、スタートアップとしては、かかる指摘を根拠に、買取請求の事由を重大な投資契約違反に限定するように投資家と交渉することが考えられます。
(2) 表明保証違反
表明保証違反についても、スタートアップ側としては、「スタートアップとの事業提携及びスタートアップへの出資に関する指針」での上記指摘を根拠に、重大な表明保証違反のみを対象とするよう投資家と交渉することが考えられます。
なお、法律論として少し細かいことを説明すると、表明保証とは、発行会社又は経営株主が自身の状況を説明するものであり、これによって何かの行為をなすべき「債務」を負うものではありません。そのため、表明保証された内容が真実と異なっていた場合であっても、民法上の債務不履行に基づく損害賠償請求は難しく、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となるだけではないかという議論が成り立つ可能性があります。このような理由から、表明保証違反があった場合の効果について、投資契約に明確に定めておかないと、責任追及が難しくなる可能性があるため、投資家にとっては、表明保証違反の場合の株式買取請求権や損害賠償請求権を投資契約において明記しておくことが重要です。
(3) 株式上場の要件を満たしているのに上場しない場合
株式上場の要件を満たしているのに上場しない場合というのは、若い起業家からすると、「え、IPOできるのにしない場合って?そんなことあるの?」と不思議に思う人もいるかもしれませんが、社歴が長くなってきて、長年にわたり社長として自由に経営していると、IPOに向けていろいろと内部管理体制等を整備していくと、窮屈に感じて、「上場なんて面倒だからやめた!」として、上場を辞めてしまうケースが実在します。また、市場環境の問題からIPOを延期するケースもあります。しかし、VC(ベンチャーキャピタル)にとっては、ファンドの満期までにIPO等でのExitを確保することは極めて重要な事項であるため、IPOできるのであれば、きちんとIPOしてもらわなければならないという事情があります。この(3)の事由については、スタートアップとして、きちんとIPOする意図であるならば受け入れてもリスクが高いものではありません。
この他の事由を買取事由とするケースもありますが、スタートアップ側の努力で該当することを回避できない事由については、スタートアップ側にとってはリスクが高いといえます。この場合は、「義務」ではなく「協議」にしたり、買取りの価格を純資産ベースなど合理的な形にするなど交渉していくことが考えられます。
3. 優越的地位の濫用との関係
「スタートアップとの事業提携及びスタートアップへの出資に関する指針」では、投資家側による以下のような行為が、独占禁止法上の優越的地位の濫用(同法第2条第9項第5号)として問題となるおそれがあると指摘されています。そのため、投資家としては、投資契約で株式買取請求権を設定する際や、実際に株式買取請求権を行使する際には、以下のような行為に該当しないように注意が必要です。
① 買取請求権を背景とした不利益な要請(知的財産権の無償譲渡等)(同指針44頁)
② 出資額よりも著しく高額な価額での買取請求が可能な買取請求権の設定の要請(同指針45頁)
③ 行使条件を満たさない株式買取請求権の行使(同指針46頁)
4. 買取請求の対象者
株式買取請求権の対象者が誰かということはとても重要で、スタートアップと投資家との交渉においても、論点となることが多いです。
発行会社が株式を買い取ることができればよいのですが、日本の会社法では、自己株式の取得については、買取金額は分配可能額の範囲内に限られるという財源規制があり、特にスタートアップの場合は、投資された資金を使ってビジネス展開をしており、分配可能額が存在しないケースがほとんどです。そのため、発行会社が自己株式を取得することは通常はできず、発行会社に対する株式買取請求権は実効性が乏しいことがほとんどです。
このような理由から、やむを得ず、会社を実質的にコントロールしているはずの経営株主に対しても、株式買取請求権を行使できるという建付けとすることが、日本の投資契約では一般的でした。
この点について、「スタートアップとの事業提携及びスタートアップへの出資に関する指針」では、「経営株主等の個人に対する買取請求が可能な株式の買取請求権については、スタートアップの起業後に経営株主となることが多い創業者にとって、出資者からの出資を受けて起業しようとするインセンティブを阻害することとなると考えられる。このため、スタートアップの起業意欲を向上させ、オープンイノベーションや雇用を促進していく観点からは、出資契約において株式の買取請求権を定める場合であっても、その請求対象から経営株主等の個人を除いていくことが、競争政策上望ましいと考えられる。」(同指針47頁)とされています。
上記3.の①②③とは異なり、経営株主を株式買取請求権の対象者とすることは、それが直ちに独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれがあるということまでは言及しておらず、投資家からの出資を受けて起業しようとするインセンティブ等の観点から望ましくないという指摘にとどまっています。
もっとも、スタートアップ側としては、このような指摘があることを根拠として経営株主を株式買取請求権の対象者から除外するように投資家と交渉することは考えられます。また、(ⅰ)経営株主が買取義務を負う場合を経営株主自身が投資契約に違反した場合に限定する(発行会社による投資契約違反の責任を経営株主個人に連帯して負わせないようにする)ことや、(ⅱ)第一次的には発行会社に対して買取請求を行い、会社法上の財源規制等により発行会社が買い取ることができない場合に限って経営株主に対する買取請求も認めるといった内容とするように投資家と交渉することも考えられます。
5. 買取価格
買取価格は、以下に基づき定めるケースが多いです。
① 投資家の取得価額
② 財産評価基本通達に定められた「類似業種比準価額方式」に従って計算した金額
③ 直近の貸借対照表の簿価純資産に基づく1株あたりの金額
④ 直近の発行又は譲渡の事例の価額
⑤ 第三者が評価した価額
実際は、株式買取請求権が行使される事態の場合には、「①投資家の取得価額」が主張されるケースが多く、これがかなりの高額になる可能性があります。この点で、スタートアップにとっては大きな責任になる可能性があり、特に経営株主が株式買取請求権の対象者となる場合には、経営株主個人が大きな責任を負うことになる可能性があるため、上記の株式買取請求権の買取事由とともに、慎重に確認検討する必要があります。
なお、少し細かい点ですが、スタートアップにとっては、上記④の「直近」について、過去のかなり以前の取引事例になってしまう可能性もあるため、例えば過去6ヶ月以内のもの等に限定するべきことを検討した方がよいと考えます。また、⑤の第三者の選定をどうするべきかについても明確化した方がよいです。さらに、株式分割等が生じた場合の調整についても、念のため明記しておくべきであると考えます。
投資家にとって注意するべき点としては、買取価格について、交渉の妥協の産物として、「協議で定める」としてしまうケースがありますが、このようにすると協議が調うまで買取価格が決まらないため、訴訟等の法的な手続に基づいて、回収することはほぼ不可能になってしまう点です。株式買取請求権を重要なサンクションとして規定する場合には、その実効性を担保するため、買取価格が一義的に明確に決まるように定めておく必要があります。
6. まとめ
今回は、スタートアップと投資家との間でも、大きな交渉ポイントとなる株式買取請求権について解説いたしました。
株式買取請求権は、それが行使される場面では、スタートアップと投資家との間で大きな対立関係が生じることから、双方にとってセンシティブな問題ではありますが、そのような重要な問題であるからこそ、スタートアップと投資家の双方が、株式買取請求権の内容についてよく理解したうえで交渉することが大切であると考え、このブログを執筆させていただきました。
本稿がスタートアップと投資家との交渉の前提としての株式買取請求権に関する理解の一助となれば幸いです。